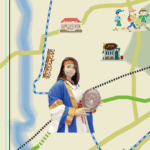楯築ルネッサンス
志ある仲間たちが集い、楯築遺跡復元プロジェクトが立ち上がった。給水塔の撤去と削られた双方部の復元を実現するためには、皆様のご支援が必要です。日本の礎を築いたのは紛れもなく吉備であり、この楯築遺跡がそれを証明してくれています。一人でも多くの方々に、このプロジェクトにご賛同を頂き、この大切な楯築遺跡を元の姿とし、古代吉備王国の誇りを取り戻しましょう。

松本直子先生 講演会
楯築ルネッサンス総会 記念講演 「新しい学問分野、文明動態学って何だろう?」 参加申込 Click 講師:松本直子(岡山大学 考古学教授・文明動態学研究所副所長) 会期:2025年6月27日(金)18時~ […]

Dr.松本申込み転送
転送 松本直子直子先生講演会申し込みフォームに1秒後に、自動転送されます。 申し込みフォームのページは、
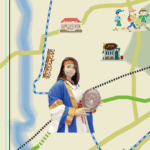
吉備路エリア未来構想案
吉備路エリア未来構想案:郷土の歴史と自然を楽しみながら学べる地域創造 岡山県の吉備路エリアには、弥生時代や古墳時代における日本誕生の歴史を語る上で欠かせない遺跡群が点在しています。この地域を「家族で楽しめる」だけでなく、 […]

古代史ツアー
【古代史ツアー詳細】 備前→赤磐方面 日時;2025/1/19 9:10 集合場所; 瀬戸内市長船町公民館 (岡山駅JR赤穂線8:30発―長船駅9:00着―徒歩8分500m) *衣装に着替えの方は8:30現地 […]